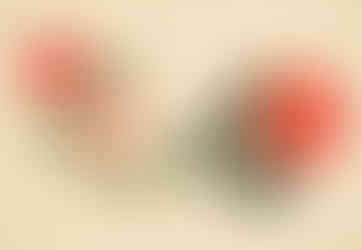毛利梅園:梅園画譜に息づく生命、江戸本草学の光芒
- 2025年5月23日
- 読了時間: 10分
更新日:2025年6月20日
1. 時を超えて息づく、自然へのまなざし
日本の花卉/園芸文化は、単なる植物の栽培に留まらず、自然への深い敬意と、その中に美を見出す独自の哲学が息づいています。あなたは、江戸時代の知られざる博物学者、毛利梅園(もうり ばいえん)が遺した『梅園画譜(ばいえんがふ)』をご存知でしょうか?この膨大な図譜は、彼が生涯をかけて追求した「真写」の精神が凝縮されており、当時の日本の自然観、そして花卉文化の奥深さを現代に伝えています。
本稿では、『梅園画譜』がどのような背景から生まれ、どのような文化的意義を持つのかを深く掘り下げ、日本の花卉・園芸文化の歴史に興味を持つ方々、そして日本の伝統に触れたいと願う方々に、その本質と魅力を余すことなくお伝えします。
2. 『梅園画譜』とは:江戸の博物学が結実した図譜
2.1. 『梅園画譜』の概要と全体像
『梅園画譜』とは、江戸時代後期に旗本であり本草学者であった毛利梅園(諱は元寿)が、生涯をかけて制作した多岐にわたる動植物の精密な写生図譜の総称です。この図譜は、魚類をまとめた『梅園魚譜』、草木や花をまとめた『梅園草木花譜』、鳥類をまとめた『梅園禽譜』など、様々なジャンルを網羅しており、その数は膨大です。梅園は、道端の植物から海産物、鳥、虫、菌類、さらには岩石に至るまで、あらゆる自然物を対象としました。
2.2. 「実写」へのこだわりと先進性
梅園の作品の最大の特徴は、「実物を見て描く」という「実写」への徹底したこだわりです。当時の写生図譜には模写が多い中で、梅園は自ら採集したものや、知人から得た「実物」を丹念に観察し、筆を執りました。その筆致は非常に生き生きとしており、構図もダイナミックで、単なる記録を超えた訴えかける力を持っています 。彩色も含め、幕臣が自ら描いたとは思えないほどの高いレベルに達しており、初めて江戸時代の博物画を見る人にも強く推奨される作品群です。
さらに、梅園は写生日や、それが実写か模写か、そしてしばしば入手元までを詳細に記録しており、この点は当時の図譜としては非常に先進的であると評価されています。この「実写」へのこだわりは、単なる芸術的表現に留まりません。江戸時代の「本草学」は、薬草の正確な同定が極めて重要であり、名前の不一致が患者の命に関わる可能性すらありました。そのため、薬草の名前と特徴を整理した正確なリファレンスが求められていたのです。梅園の精密な描写は、このような科学的な正確性を担保する上で不可欠であり、彼の作品は、科学的な探求心と、それを支える精密な観察・記録技術が融合した結果として位置づけられます。
一方で、梅園の先進性は、当時の本草学が経験主義的・実証的な方向へ進んでいたことを示唆しています。しかし、梅園の作品には縮尺が示されておらず、分類学への意識が低い点が指摘されています 。これは、当時の日本の博物学が、中国からの知識を基盤としつつも、国内資源の調査や品種改良が進み、西洋の知識も取り入れられながら、まだ近代的な分類学の体系化には至っていなかった、あるいはその必要性を強く認識していなかった段階にあったことを示しています。したがって、『梅園画譜』は、実物に基づいた詳細な記録という点で画期的ながらも、近代科学的な体系化という点では発展途上にあった当時の学術的状況を反映する作品であると言えるでしょう。
3. 歴史と背景:旗本・毛利梅園の生涯と江戸本草学の潮流
3.1. 毛利梅園の足跡:好奇心に導かれた生涯
毛利梅園は、寛政10年(1798)に江戸幕府旗本・毛利兵橘元苗の長男として生まれ、嘉永4年(1851)に54歳でその生涯を閉じました。諱は元寿(もとひさ)です。彼は幕府の直参である旗本として職務に励む傍ら、本草学者としての卓越した業績を残しました。
文政3年(1820)頃から植物に興味を持ち、写生に熱中するようになりました。当初は屋敷内に「梅樹園」と号する庭園を設け、後に阿部正精から「欑華園(さんかえん)」の号を賜るほどでした。彼は江戸近郊へも積極的に採集に出かけ、嘉永元年(1848)9月には高尾山、嘉永2年(1849)3月には箱根で採集を行い、その他にも小仏峠、大山、江ノ島、鎌倉、金沢など、広範囲を巡りました 。この旺盛なフィールドワークが、『梅園画譜』の写実性を支える基盤となりました。天保2年(1831)には動物、天保6年(1835)には菌類へと関心を広げ、多岐にわたる対象を記録していきました。
梅園が「旗本」という幕府の職務に就きながら、「本草学者」として写生に熱中し、膨大な図譜を残した事実は、当時の江戸知識人の多様な側面を映し出しています。江戸時代には、武士が単なる軍事・行政の担い手であるだけでなく、教養人としての側面も重視され、職務の傍ら学問や芸術に深く傾倒する例が少なくありませんでした。梅園の事例は、知的好奇心が身分や職務の枠を超えて個人の情熱を追求する原動力となったことを示しています。特に、実学としての本草学は、武士の教養としても奨励される傾向にあったため、梅園の業績は、公務と私的な学術活動を両立させた、当時の知識人の典型的な姿を象徴していると言えるでしょう。
3.2. 江戸時代の本草学と園芸文化:知的好奇心の時代
江戸時代は、中国から伝わった「本草学」が日本独自の発展を遂げた時代です。初期は薬草の知識が中心でしたが、次第に鉱物、動物、植物など、あらゆる自然物を対象とする「博物学」へと広がっていきました。この学問は、単に薬の知識を得るだけでなく、名前とモノの一致を重視し、誤認による危険を避けるための「リファレンス」作成という実用的な目的も持っていました。本草学の精神は、喜多川歌麿や伊藤若冲といった同時代の絵師たちにも影響を与え、生き生きとした動植物を精緻に描いた「本草画」が多数残されています。
江戸時代後期には、庶民の間でも園芸が盛んになり、独特の美意識が花開きました。現代の園芸植物とは異なり、花弁の形や模様、葉の斑入りなど、繊細な変化の中に美を見出す点が特徴です。アサガオの「変化朝顔」や、キク、オモト、イワヒバ、カンアオイ、マツバラン、ナンテンなど、多様な古典園芸植物が品種改良され、その奇妙な形や斑入りが愛でられました。「花合せ」と呼ばれる品評会が盛んに行われ、優れた品種には「番付」が付けられ、「銘鑑」という登録簿に記録されるなど、園芸は一大文化として栄えました。
江戸時代の本草学と園芸文化は、互いに影響を与え合い、相乗効果を生み出しました。本草学の発展は、植物への知的好奇心を高め、その知識は園芸における品種改良や栽培技術の進歩に貢献したと考えられます。逆に、園芸ブームは、新たな植物の発見や記録の需要を生み出し、本草学の対象範囲を広げる一因となりました。梅園の『梅園画譜』は、薬用植物だけでなく観賞用植物も網羅する点で、この両者の融合を体現していると言えるでしょう。梅園の作品は、学術的な探求と大衆の美意識が交差する、当時の知的な活況を示す具体的な証拠となっています。
4. 文化的意義と哲学:『梅園画譜』に宿る「不易流行」の精神
4.1. 「真写」の追求と自然への敬意
毛利梅園が徹底した「実写」の追求は、単なる写実的な描写技術の高さに留まりません。それは、対象となる生命体、すなわち植物や動物、菌類といった自然の「ありのままの姿」を深く理解し、尊重しようとする精神性の表れです。梅園は、実物を観察し、その生命の息吹を紙の上に写し取ることで、自然界の精妙な秩序と多様性を捉えようとしました。これは、当時の日本人が自然に対して抱いていた畏敬の念と、その中に美を見出す独自の美意識が色濃く反映されています。梅園の作品は、細部にわたる観察眼と、それを正確に再現する筆致によって、対象が持つ生命力や躍動感を表現しており、「とりあえず記録しました」というレベルをはるかに超えた、見る者に何かを訴えかける力を持っています。
梅園の徹底した実写主義の中で、特異な存在感を放つのが、『梅園魚譜』に描かれた「人魚図」です。老男性のような姿で描かれたこの人魚は、梅園の実物主義からは一見矛盾しているように見えます。しかし、これは当時の博物学が、実証的な観察と同時に、伝承や伝説、あるいは「報告された現象」をも記録の対象としていたことを示唆しています。江戸時代の自然観は、現代の科学的視点とは大きく異なり、美的感覚も違っていました。本草学は、薬草の同定という実用性から発展しましたが、同時に伝統的な美意識や思想も影響を与えていました。梅園の「真写」は、単なる西洋的な科学的写実主義の導入ではなく、日本の伝統的な自然観、すなわち自然の中に宿る生命力や精神性を捉えようとする美意識と融合していたのです。人魚図の存在は、梅園の観察が、単なる客観的記録だけでなく、当時の社会が共有する「自然」の概念全体を包括しようとする試みであったことを示唆しています。このように、『梅園画譜』は、江戸時代における科学的探求の萌芽が、まだ伝統的な自然観や伝承と分かちがたく結びついていた時代の、貴重な証言であると言えるでしょう。梅園は、単に「見たまま」を描くのではなく、「信じられていたもの」も含めて「自然」として捉え、記録しようとした点で、当時の知のダイナミズムを体現しています。
4.2. 科学と芸術の融合:時代の潮流を映す鏡
『梅園画譜』には、日本の花卉/園芸文化の根底にある「不易流行(ふえきりゅうこう)」の哲学が込められています。これは、流行は移り変わっても、根本にある美意識や自然への敬意は変わらないという思想です。梅園の「真写」は、まさにこの「不易」の部分、すなわち自然の普遍的な姿を捉えようとする試みと言えます。この思想は、当時の博物学における「脱季語性(だつきごせい)」の萌芽とも関連しています。これは、植物を季節の象徴としてだけでなく、より普遍的な「モノ」として認識しようとする動きであり、梅園の作品は、伝統的な美意識と近代的な科学的視点が交錯する、江戸時代の知のダイナミズムを象徴しています。
『梅園画譜』は、単なる学術的な図譜としてだけでなく、当時の人々の植物への関心の高まりに応えるものとして、市場的な価値も持っていたと考えられます。江戸時代には園芸ブームが起こり、珍しい植物や美しい図譜への需要が高まっていました。梅園の作品は、その精密な描写と芸術性の高さから、学術的な資料としての価値に加え、観賞用としての魅力も兼ね備えていました。これは、芸術的革新と大衆の需要が合致した結果生まれた、時代の潮流を象徴する作品であり、当時の文化経済の活況を示す具体的な証拠であると言えるでしょう。『梅園画譜』は、江戸時代における伝統的な美意識と、近代的な科学的探求心、そして大衆文化の活況が複雑に絡み合った、多層的な知のダイナミズムを映し出す鏡であると言えます。梅園は、その作品を通じて、自然を多角的に捉え、その本質を深く探求しようとした時代の精神を現代に伝えているのです。
5. 結び:現代に語りかける『梅園画譜』の魅力
毛利梅園の『梅園画譜』は、単なる過去の博物画集ではありません。それは、江戸時代の知的好奇心と、自然への深い愛情、そして「真写」という揺るぎない探求心が結実した、まさに生きた文化遺産です。
梅園の作品は、現代を生きる私たちに、足元の植物や身近な自然の中に潜む無限の美と驚きを再発見する視点を与えてくれます。また、目まぐるしく変化する現代社会において、「不易流行」の精神を思い起こさせ、変わらない自然の尊さや、それに対する敬意の重要性を教えてくれます。『梅園画譜』を通じて、私たちは江戸時代の人々がどのように自然と向き合い、その中にどのような美を見出していたのかを追体験することができます。この図譜が、日本の花卉/園芸文化への関心をさらに深め、私たちの暮らしに豊かな彩りをもたらすきっかけとなることを願っています。
梅園草木花譜
春之部

夏之部

秋之部

冬之部

梅園海石榴花譜
毛利元寿梅園<毛利梅園>//模写『梅園海石榴花譜』,写,天保15(1844).国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1286917
草木実譜
毛利梅園『草木実譜』,写.国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/2537209