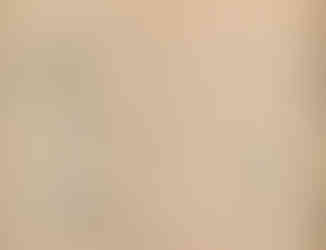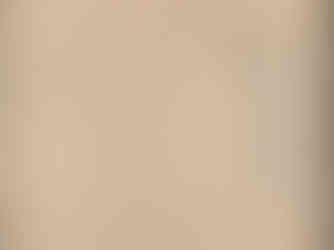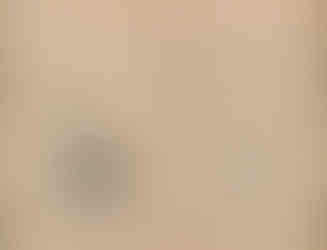飯沼慾斎の『草木図説』:近代日本植物学の礎石
- JBC
- 2025年1月3日
- 読了時間: 22分
更新日:2025年6月20日
1. 序論:飯沼慾斎と近代日本植物学の黎明
飯沼慾斎の著作『草木図説』は、日本の植物学史における画期的な出来事であり、伝統的な日中本草学から、西洋の影響を受けた近代的な科学的植物学への重要な転換点を示すものです。この著作は、日本初の近代的植物図鑑と広く認識されています。本稿では、この記念碑的著作の著者である飯沼慾斎の生涯と学問的背景を概観し、『草木図説』の歴史的文脈、革新的な方法論、同時代の著作との比較、そして日本の植物科学の発展における永続的な遺産について詳細な分析を行います。江戸時代は本草学が隆盛を極めましたが、『草木図説』は、この伝統と、特にリンネ分類法を中心とする新たな西洋植物学とを独自に融合させた著作として際立っています。
『草木図説』が持つ「混成性」は、日本の植物学近代化を促進する上で触媒的な役割を果たしたと考えられます。伝統的な本草学は、その豊かさにもかかわらず、体系的な分類において限界があり、しばしば古代中国の文献に依存していました。一方、西洋植物学、特にリンネの分類体系は、植物界を理解するための新しい構造化された枠組みを提供しました。慾斎は本草学を単純に否定するのではなく、その限界を認識し、それを強化しようと試みました 。西洋の手法(リンネ体系、顕微鏡観察)を既存の知識基盤や図解の伝統(洗練されたものではあったが)と統合することで、慾斎は革新的でありながら、その後の日本の植物学研究に影響を与えるのに十分なほど受容されやすい著作を生み出しました。これは完全な断絶ではなく、変革的な進化でした。この混成性は、おそらくその受容と影響にとって極めて重要であったでしょう。伝統的な形式を完全に拒絶すれば、より大きな抵抗に直面したかもしれません。代わりに『草木図説』は橋渡しとなり、日本の植物学を近代化へと導いたのです。
2. 飯沼慾斎(飯沼長順)の生涯と学問的探求
飯沼慾斎、名は長順、慾斎は号です。天明2年(1782)または天明3年(1783)に伊勢国亀山(現在の三重県亀山市)に生まれました。美濃国大垣(現在の岐阜県大垣市)の医師、飯沼長顕の養子となりました。養父のもとで医学を修め、後に京都で福井丹後守にも学びました。蘭方医として名声を確立し 、文政12年(1829)には弟子と共に岐阜県下で初の人体解剖を行い、医学の発展にも貢献しました。
医学の実践と並行して、本草学への深い関心を育み、本草学の大家である小野蘭山に師事しました。この指導は彼の植物学研究の基礎となりました。50歳で医業を退き、植物学研究に専念するため、大垣郊外に別荘「平林荘」を建てました。この平林荘で約30年間にわたり集中的な研究と観察を行い、70歳頃に『草木図説』を完成させたとされます。元治2年(1865)に没しました。
慾斎の知的探求は、伝統的な本草学への批判意識と、西洋の学問(蘭学)への積極的な関与によって特徴づけられます。彼は、当時の本草学が植物の漢名を特定することに偏重し、より深い植物学的研究を怠っていると不満を表明し、「余の望む所の植学者と大いに同じからず」(私が志す植物学者とは大きく異なる)と述べています 。この批判意識が、観察に基づいた新たな植物図説を作成する動機となりました。彼は西洋の植物学書を熱心に研究し、原書が希少であったため、しばしば自ら筆写しました。特に影響を受けたものとして、ミュンチングの『アールドゲワッセン』やクニホフの『植物印葉図譜』などが挙げられます 。また、伊藤圭介の『泰西本草名疏』や宇田川榕菴の『植学啓原』といった、西洋植物学を紹介した同時代の日本の著作からも指導を受けました 。伊藤圭介のような学者たちとは、年齢差があったにもかかわらず、慾斎は積極的に交流し、新しい知識を熱心に吸収しました 。この知的な謙虚さと好奇心が、彼の業績にとって不可欠でした。
慾斎の経歴において、医師としての訓練が植物学者としての彼の精密な観察眼を育んだことは注目に値します。蘭方医学の訓練は、経験的観察と解剖学的理解を重視するものであり、これが植物研究にも応用され、顕微鏡を用いた微細な構造の観察へと繋がったと考えられます。50歳で医業を引退し、その後30年もの歳月を『草木図説』の完成に捧げたという事実は、単なる趣味を超えた、生涯をかけた事業としての並外れた献身を示しています。この医師としての背景が、彼の植物学研究に独自の厳密さと観察の鋭敏さをもたらし、『草木図説』を際立たせる要因となったと言えるでしょう。
また、慾斎が50歳で医業から引退し、平林荘という研究拠点に身を置いたことは、その学術的生産にとって決定的な意味を持ったと考えられます。多忙な医療業務は、『草木図説』のような広範かつ集中的な研究に必要な時間を制約したでしょう。引退は、この新しい学術的探求に専念するための時間的・知的な自由をもたらしました。「学問的引退」というこのモデルは、江戸時代において、特に新たな地平を切り開こうとする大規模で時間のかかる事業に着手する上で、重要な条件であったと考えられます。
3. 『草木図説』:出版、範囲、構成
『草木図説』は、全体で40巻からなる壮大な計画でした 。その出版史は複雑で、慾斎の生前と死後にまたがります。
出版の経緯
前編・草部
20巻20冊で構成されます。
嘉永5年(1852年)頃に完成したとされ 、安政3年(1856年)から文久2年(1862年)にかけて逐次出版されました。出版は平林荘(慾斎の号を冠した書肆)によるものです。
木部
10巻が計画されていました。
慾斎の生前には出版されず、稿本の形で残されました。1977年(昭和52年)に、これらの稿本を基にして初めて出版されました。
未刊の部
計画された40巻のうち、残りの10巻は未刊に終わりました。
禾本、莎草、無花部に関する稿本は、未整理のまま残されました。
範囲と内容
収録種数
草部:約1200種から1250種 。は草本類1205種と特定しています。
木部:約600種 。は木本類597種と特定しています。
慾斎自身の観察によって確認された日本固有の植物および一部の舶来種を含むとされます。
命名法
植物名は主に和名で統一され、慾斎によって標準化が試みられました。
多くの場合、ラテン名またはオランダ名が付記されました。
一部の植物には漢名が補足情報として添えられました。
構成と体裁
通常、左頁に植物図、右頁に解説文が配置されました。
解説には、植物名、生育環境、特徴、構造などが記されました。
本文は片仮名交じり文で書かれました。
稿本
慾斎はいくつかの稿本を残しました。特に注目されるのは、慾斎自筆とされ、豊かで繊細な彩色が施された江崎家本27巻です。木部の稿本も存在し、一部は慾斎の自筆です。木部の稿本は明治5年(1872)に政府に献納され、現在は高知県立牧野植物園に所蔵されていると考えられています。また、『草木図説遺稿』と呼ばれる別の稿本群には、万延元年(1860)の遣米使節や文久2年(1862)の遣欧使節が持ち帰った種子から育てた植物が記録されており、これらは出版された草部にはほとんど反映されませんでした。この遺稿は現在、岐阜市歴史博物館に寄託されています。
表1:『草木図説』の出版と内容概観
部 | 原計画巻数 | 慾斎生前出版巻数 | 後世出版巻数(年) | 推定収録種数 | 主な出版時期 |
草部 | 20巻 | 20巻 | - | 約1205種 | 1856年~1862年 |
木部 | 10巻 | 0巻 | 10巻 (1977年) | 約597種 | (1977年) |
他 | 10巻 | 0巻 | 未刊 | 不明 | - |
合計 | 40巻 | 20巻 | 10巻 | 約1802種以上 |
『草木図説』の壮大な構想と、その一部しか生前に実現しなかったという事実は、慾斎の並々ならぬ献身と野心、そして当時の学術出版が直面した困難さを物語っています。草部だけで1200種以上、木部と合わせると1800種を超える植物を一人で観察し、図示し、記述するという作業は、たとえ30年の歳月を捧げたとしても、個人にとっては膨大なものであったでしょう 。それぞれの種について、観察、図解、記述を行い、さらに木版彫刻と印刷という工程を経ることは、信じられないほど時間と費用を要するものでした。生前にかなりの部分が未刊に終わったという事実は、当時の日本において、このような大規模な科学的記録事業がいかに困難であったかを示しており、資金、健康、あるいは単に野心の規模そのものが要因であった可能性が考えられます。それにもかかわらず、『草木図説』は、部分的に実現された出版形態においてさえ、慾斎の計り知れない努力と先見性の証左として屹立しています。
4. 『草木図説』における先駆的な方法論
4.1 リンネ分類法の採用
『草木図説』が画期的であった最大の理由の一つは、カール・フォン・リンネの24綱分類法という、植物の性的器官に基づく分類体系を導入したことです。これは、しばしば実用性や外形的特徴に基づいていた伝統的な本草学の分類法からの大きな転換を意味しました。さらに、属名と種小名からなるリンネの二名法も採用されました。和名が主たる名称とされたものの、ラテン名やオランダ名の併記、あるいはその意図は、国際的な植物学との接続を意識したものであったと考えられます。この体系的なアプローチは、日本の植物研究の精度と科学的有用性を著しく向上させ、その後の研究の基礎を築きました。慾斎がリンネ分類法を知るに至ったのは、主に伊藤圭介を通じてでした。伊藤圭介はフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトに学び、リンネの弟子であるツュンベリーの『日本植物誌』の一部を自身の『泰西本草名疏』で紹介していました。
慾斎がリンネ体系を導入したのは、単に既存の植物に新しいラベルを貼るという以上の意味を持っていました。彼はこの体系を用いて1800種以上の植物を整理し、記述しました。慾斎の動機は、単なる名称の同定に留まらない「植学者」としてのアプローチへの渇望でした 。伝統的な本草学の分類は、薬効や食用といった実用的な側面や、一貫した全体的体系のない形態学に基づいていることが多かったのです。対照的に、リンネの生殖器官に基づく体系は、未知の植物にさえ適用可能な普遍的で予測的な枠組みを提供しました 。慾斎にとって、この体系の採用は、単に外国語の名前を追加することではなく、植物がどのように理解され、関連づけられ、研究されるかという方法を根本的に再構築することでした。それは、より分析的で体系的な植物学への概念的転換を意味しました。これにより、確立された薬局方の範囲を超えて、植物界とのより「科学的な」(西洋で勃興しつつあった意味での)関わりが可能になったのです。リンネ分類法の採用は、『草木図説』の近代性を駆動する知的エンジンであり、日本の植物学が記述的本草学から分析的植物学へと移行する狼煙となったのです。
4.2 植物図の革新
『草木図説』の図版は、その科学的価値を高める上で不可欠な要素でした。
正確な写生図への重点:図は生きた植物の綿密な直接観察に基づいて描かれました。これは、図が様式化されたり、中国の文献から模写されたりすることもあった初期の本草学の著作とは対照的です。
部分図と顕微鏡観察による詳細図の導入:慾斎は、花や種子などの特定の植物部位の詳細な図を収録し、構造的特徴を示しました。決定的に重要なのは、日本で初めて顕微鏡を用いて植物の微細な解剖学的特徴を観察し、植物学出版物のために描画したことです。嘉永4年(1851年)に伊藤圭介から高倍率の顕微鏡を入手したことが、これを可能にしました。
独特な葉の描画技法:特徴的なのは、葉の表面を黒く、裏面を白く(あるいはその逆、情報源により若干の差異があるが、区別が重要)描くことで、立体感や質感を表現する手法です。およびによれば、『草木図説』では葉の表面を黒く塗りつぶし葉脈を白く浮き立たせ、裏面は白く葉脈を黒く描く方法がとられました。これは、師である小野蘭山が『花彙』で用いた、裏面を黒くする技法とは逆でした。この意図的な選択は、慾斎が明瞭さのために技法を洗練させていたことを示唆しています。
印葉図の活用:慾斎は、生乾きの植物に墨を塗り紙に押し付けて直接的な写しを得る、ヨーロッパのこの技法(ネイチャープリンティング)を採用し、葉脈などの微細な細部を捉えました。彼の稿本には約57点の印葉図が含まれています。これらは、特にシダ類やキク科植物など、複雑な葉の構造を持つ植物に対して、主たる図を補足する形で、特に微細な部分の表現のために用いられました。彼がこの技法を学んだのは、自ら筆写したクニホフの『植物印葉図譜』のような著作からであった可能性が高いです。
印刷と彩色:出版された『草木図説』は主に木版画で印刷されました。慾斎は、より詳細な表現が可能だったかもしれない西洋の銅版画ではなく、伝統的な木版印刷を意識的に選択しました。これは、費用、利用可能な専門技術、あるいは師である蘭山の『花彙』に倣った美的嗜好によるものかもしれません。慾斎の原稿はしばしば美しく手彩色されていましたが 、出版された版は費用を抑えるために大部分が単色(白黒)でした 。出版された版の一部の部分図には手彩色が施されました。現存する一部の写本には、後世の、おそらくは私的な手彩色が施された形跡が見られます。
出版における現実的な判断、すなわち単色刷りという妥協は、当時の科学出版が直面した経済的制約を浮き彫りにします。多色木版印刷は複雑で高価であり、数千もの図版を含む多巻物の著作にとって、全ページフルカラー印刷の費用は法外なものとなり、普及を著しく制限したでしょう。慾斎(あるいは版元)は、色彩による完全な美的表現よりも、より広範なアクセスと科学的情報(線と陰影による形態、構造)の伝達を優先するという現実的な選択をしたのです。葉の描画法のような革新的な単色技法は、白黒印刷の制約の中で視覚情報を最大化する試みと見ることができます。手彩色の稿本の存在は慾斎の理想を示し、出版された形態は普及のための彼の現実的なアプローチを示しています。
顕微鏡の導入は、観察の深度における飛躍でした。慾斎が日本で初めて植物図に顕微鏡を用いたことは 、リンネ分類法が依拠する雄蕊や雌蕊といった微細な形態学的詳細を捉える上で決定的に重要でした。肉眼では限界があるこれらの構造を、顕微鏡は新たなレベルの精度で描き出すことを可能にしました。これは単に美しい図版を作成するためではなく、新しい分類体系が必要とする形態学的データを捉えるためでした。慾斎による植物図への顕微鏡導入は、リンネ分類法への科学的転換を直接的に支える重要な技術的採用であり、日本の植物観察と表現の基準を根本的に変えました。
5. 比較分析:江戸時代の本草学における『草木図説』
5.1 伝統的本草学からの脱却
伝統的な本草学は、中国の薬物学(例えば李時珍の『本草綱目』)に強く影響され、しばしば薬効や文献的権威を優先していました。慾斎は、この伝統の中で(『本草綱目啓蒙』の著者である小野蘭山のもとで)訓練を受けましたが 、植物そのものの直接観察、その形態学、そして体系的分類に基づく植物学へと舵を切りました。これは、主に実用性や文献上の系統に焦点を当てることからの一線を画すものでした 。慾斎は、本草学者が日本の植物を中国の古典籍中の名称と関連づけることに終始する傾向を明確に批判し、より経験的な「植学者」的アプローチを望みました。
5.1 同時代の植物図譜との比較
岩崎灌園『本草図譜』(1828年頃~1844年)
約2000種を描写することを目的とした大規模な著作でした。しかし、依然として伝統的な本草学の枠組みに大きく依拠し、『本草綱目』の体系に従っていました。
図版は広範でしたが、『草木図説』と比較すると、しばしばより簡略化されているか、科学的精度が低いと評されます。『草木図説』は、部分図や顕微鏡による観察図を含め、より高い正確さと詳細さを目指しました。
『本草図譜』はしばしば美しく彩色されていました。
『草木図説』のリンネ分類法の採用と詳細な形態学への焦点は、『本草図譜』よりも西洋の科学的植物学との連携が強いことを示しています。は「『本草図譜』は、中国の本草学に基づいており、図は簡略化されていました。一方、草木図説は、西洋の植物学を取り入れ、リンネの分類法を採用することで、より科学的な記述と正確な図を実現しました」と述べています。
『花彙』(小野蘭山、島田充房、1765年)
美しい、しばしば彩色の施された木版画で知られます。美的価値は高いものの、その主目的は体系的な植物科学よりも、顕花植物の描写と鑑賞にあった可能性が高いです。慾斎は蘭山の『花彙』における図示技法から学んだが、それを(例えば葉の陰影法のように)改作しました。
は、『花彙』のような著作が美しい彩色図を持っていたのに対し、『草木図説』は単色刷りでありながらも、細部の正確な描写を優先したと指摘しています。
『絵本野山草』
『花彙』と同様に、美的描写に重点を置き、しばしば彩色されていたと考えられます。『草木図説』は、主に白黒の体裁でありながらも科学的正確性を重視した点で、これらとは対照的です。
牧野富太郎の後年の著作:
『草木図説』は大きな前進でしたが、西洋の印刷水準に匹敵する真に高品質な植物図版は、後の牧野富太郎の業績によって達成されたと指摘されています。これは、日本の植物図解の継続的な進化に関する視点を提供します。
表2:『草木図説』と主要な同時代著作の比較特徴
特徴 | 『草木図説』(飯沼慾斎) | 『本草図譜』(岩崎灌園) | 『花彙』(小野蘭山他) |
主要分類体系 | リンネ24綱分類 | 伝統的本草学(本草綱目体系) | 主に形態学的、実用的 |
図の様式(詳細度、正確性) | 高い、写実的、部分図、顕微鏡図あり | 比較的簡略化、網羅的 | 美的、装飾的 |
彩色(出版時) | 主に単色(一部部分図に手彩色) | 多くが彩色 | 多くが彩色 |
顕微鏡図の有無 | あり | なし | なし |
主要な影響源 | 本草学と西洋植物学の融合 | 中国本草学 | 本草学、園芸 |
主目的 | 科学的記録、体系的分類 | 本草学的同定、網羅的記録 | 鑑賞、本草学的情報 |
『草木図説』における図版の「科学的転回」は、その歴史的意義を理解する上で極めて重要です。『本草図譜』や『花彙』のような同時代の著作と比較して、『草木図説』の図版は、しばしば単色であったにもかかわらず、より高い科学的正確性を目指し、部分図や顕微鏡による詳細図を取り入れました。日本の初期の植物図は、薬用としての同定や美的鑑賞といった目的を果たすことが多かったのです。それらも価値あるものでしたが、微細な特徴の科学的精度が常に最優先されたわけではありませんでした。慾斎によるリンネ分類法の採用は、その体系が依拠する形態学的詳細(特に花の構造)への焦点を必然的に伴いました。したがって、彼の図版は単なる表現ではなく、科学的分析と記録のための道具となったのです。顕微鏡の使用は、この転換の最も明確な例です。『草木図説』は、日本の植物図解における決定的な「科学的転回」を示しており、図像が分類と理解という科学的手法に不可欠なものとなり、純粋に記述的あるいは美的役割を超えたものとなったのです。
6. 『草木図説』の永続的遺産と評価
6.1 日本植物学の近代化への影響
『草木図説』は、日本の植物学を近代化へと導く上で極めて重要な役割を果たしました。リンネ分類法の採用と経験的観察の重視は、日本の植物研究の精度と方法論を向上させました。その結果、後の植物図鑑や研究に大きな影響を与え、基礎的な参考文献となりました。近代的な教育制度が確立される以前の時代に、このような科学志向の植物百科事典が登場したことは、日本の学術史において特筆すべき出来事でした。
6.2 園芸文化への影響
主として科学的な著作でしたが、『草木図説』の詳細な図版と解説は、間接的に一般の人々の園芸への関心を高めるのに貢献したと考えられています。江戸時代は既に園芸ブームを経験しており、様々な植物への関心が広まっていました。識字率の高い庶民にもアクセス可能であった『草木図説』のような科学的に詳細な著作は、この関心をさらに刺激した可能性があります。
6.3 歴史的および現代的評価
『草木図説』は今日でも、植物学、本草学、科学史の研究において重要な資料として高く評価されています 。科学的価値を超えて、その図版(特に彩色の施された稿本)の美しさと精度は、美術的価値も認められています。この著作は国際的な注目も集めました。特に、田中芳男と小野職愨によって編纂され、フランスの植物学者リュドヴィク・サヴァティエが校閲に関与した『新訂草木図説』(1875年)を通じて、その評価は高まりました。この版は学名と科名を追記し、慾斎の業績を西洋の植物学者にもアクセス可能にし、認知されるものとしました。サヴァティエ自身も『草木図説』を高く評価し、自身の日本植物相研究に活用しました。慾斎の業績とアプローチは、牧野富太郎のような後世の著名な植物学者からも尊敬されました 。彼は、小野蘭山から慾斎や伊藤圭介のような同時代人を経て牧野へと続く、本草学から近代植物学へと移行した日本の植物学者の系譜における重要人物と見なされています。
6.4 各版
初版(草部):安政3年~文久2年(1856年~1862年)、平林荘刊。
『新訂草木図説』: 明治8年(1875年)。田中・小野編纂、サヴァティエ協力。初版の版木を用い、学名などを追記 。国立国会図書館所蔵。
『増訂草木図説』/牧野増訂版:牧野富太郎により明治40年~大正2年(1907年~1913年)に出版。本文活版、図は木版(無彩色)。牧野による大幅な改訂が加えられ、「原形をとどめていない」とも評されます。
木部の出版:1977年、保育社より北村四郎編註で稿本を基に出版。
慾斎の死後に出版された『新訂草木図説』や牧野富太郎による『増訂草木図説』は、その遺産を後世に伝える上で重要な役割を果たしました。慾斎の原著は画期的でしたが、一貫した最新の西洋式学名を欠いていました(一部ラテン名やオランダ名は含まれていましたが)。田中、小野、そしてサヴァティエによる『新訂』版は、標準化された学名と科分類を(サヴァティエの専門知識をもって)付加することで、この著作を国際的な植物学の言説と互換性のあるものにしました。これは海外での認知と、世界の科学コミュニティへの統合にとって極めて重要でした。牧野による後の改訂は、原著を大きく変容させたものの、『草木図説』というタイトルと慾斎の名を、形を変えながらも新しい世代にとって主要な植物学著作と結びつけ続けました。これらの死後の改訂と拡張は、『草木図説』の永続的な遺産にとって不可欠でした。それらは橋渡しとして機能し、慾斎の基礎的な貢献を、進化する世界の植物学の言語と基準へと翻訳し、その継続的な今日性と歴史における地位を確固たるものにしたのです。特にサヴァティエの関与は、その国際的な検証にとって鍵となりました。
7. 結論:科学史における『草木図説』の永続的意義
飯沼慾斎の『草木図説』は、日本の植物学におけるリンネ分類法の先駆的採用、顕微鏡観察や印葉図といった技法を含む観察の正確性と詳細な植物図における新基準の確立、そして純粋に実用主義的な本草学からの脱却という、いくつかの革新的な貢献によって特徴づけられます。慾斎個人の献身、日本の伝統と西洋の伝統双方への批判的関与、そして日本の植物研究の方向性を根本的に変えた著作を生み出すという彼の先見性は特筆に値します。
『草木図説』は、近代日本植物学の礎石として、伝統的知識と世界的な科学的潮流との間の重要な連結環として存在します。その影響は学界を超えて広がり、植物に対する文化的評価にも影響を与えました。この著作は単なる歴史的遺物ではなく、日本の科学的覚醒と、自然界を理解しようとする普遍的な探求の象徴です。その詳細な観察と図版は、研究者にとって価値を持ち続け、慾斎の記念碑的業績への称賛を呼び起こし続けています。
『草木図説』は、日本の科学的近代化における「概念実証」としての役割も果たしたと言えます。この著作は、外来の科学体系(リンネ分類法)を、土着の学術的伝統や芸術的伝統(洗練された木版図)と成功裏に統合しました。江戸時代、日本は蘭学を通じて西洋の知識を選択的に取り入れていました。『草木図説』は、西洋の科学的方法論が日本の文脈の中で効果的に採用、適応、応用され、質の高い独自の科学的業績を生み出すことができることを実証しました。それは、日本の学者が西洋から学ぶだけでなく、これらの新しい道具を用いて科学的記録に意義深く貢献できることを示したのです。植物学を超えて、『草木図説』は、日本がどのように科学的近代化を乗り越えることができるかを示す重要な初期の例となりました。それは、全面的な模倣ではなく、思慮深い統合と土着の革新によるものでした。これは、明治時代以降の日本のより広範な科学技術の進歩を予示する、成功した「概念実証」でした。
草部 一
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 二
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 三
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 四
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 五
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 六
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 七
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 八
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 九
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 十
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 十一
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 十二
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 十三
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 十四
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 十五
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 十六
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 十七
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 十八
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 十九
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619
草部 二十
飯沼, 慾斎 ほか『草木図説前編 20巻』,出雲寺文治郎[ほか12名],安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608619